2013年1月20日(日)は快晴。
14日の大雪から1週間近くが過ぎましたが、まだ日陰には雪が残り、かちんかちんに凍っている状況です。
 ここ数日、体調を崩していたのですが快復し、好天に誘われて埼玉・川越に向かいました。「『農』と里山シンポジウム-三富(さんとめ)を未来に-」が開催されたのです。
ここ数日、体調を崩していたのですが快復し、好天に誘われて埼玉・川越に向かいました。「『農』と里山シンポジウム-三富(さんとめ)を未来に-」が開催されたのです。
この日の会場は川越南文化会館。主催者から送って頂いたバスの時刻表をみても不便で、西武鉄道・本川越駅近くでレンタサイクルを借りることにしました。
スマホのマップを頼りに会場に向かいます。風は少々強いものの、青空の下の一人サイクリングは、それなりに快適です。
途中、砂久保稲荷神社というところに差し掛かりました。
自転車を置いて説明板の文章を読んでみると、河越合戦の際に北条軍が陣を布いた場所とのこと。小田原北条氏が戦国時代の関東の覇権を確立する大きなきっかけとなった地です。
説明板に難波田善銀の名前など見ると血が騒ぎましたが、今日はシンポジウムの会場へ。
ところで、この辺りを含む「三富(さんとめ)地域」は、元禄時代の開拓で生まれた畑作地帯で(「新田」と呼ばれます)で、屋敷、畑、雑木林からなる短冊状の地割りが特徴的です(県の文化財にも指定されています)。

この地形は航空写真では一目で分かりますが、地上からでも、農家の前に農地が拡がっており、その向こうに雑木林を望むことができます。

残った雪が冬の日を浴びて輝いています。雑木林の一部は、保全緑地として指定されています。
この雑木林は、防風のほか、燃料(薪、炭)や落ち葉による堆肥を供給するという重要な役割を担い、この地域独特の循環型農業を支えてきました。
しかし近年、化学肥料や石油・ガス等の普及、農業の後継者不足、さらには林地には農地のような転用等の規制がないこともあって、資材置き場や産業廃棄物の焼却施設用地に転用される雑木林が増加し、1999年にはいわゆる「所沢ダイオキシン騒動」の発生という苦い経験もありました。

このようなことから、「農」と里山の持続可能なシステムを未来に向けて発展させるため、三富地域農業振興協議会等からなる実行委員会の主催によるシンポジウムが開催されているのです(今回が3回目)。

挨拶に続いてのプログラムの前半は、「いのちとくらしを支える都市農業」と題し、後藤光蔵・武蔵大学教授(農林水産省「都市農業の振興に関する検討会」座長)から基調講演が行われました。
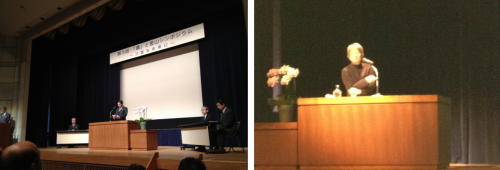
後藤先生によると、国の施策としても農地、林地を潰していく時代は終わったとのこと。
むしろ、人口減少・高齢化の中で、快適な都市空間形成のため、都市農地を資産として積極的に位置づけるべき。
ただ、私有地と生業としての農業という構造の下で、これを実現していくことは非常に難しく、制度・税制の見直しの必要性とともに、雑木林保全についての地域住民の強い意識と主体的な協働の取組が必要であること等について説明がありました。
また、都市農業の多様な機能を、農業経営の一部に取り込んで発揮している事例として、練馬区の農業体験農園について紹介されるなど、多くの示唆に富んだ講演でした。
休憩時間、ロビーでは三富地域の概要、様々な活動をされている団体に関するパネル、木工製品等の展示が行われていました。この地域の農地と雑木林の保全に、多くの関係者が関わっていることが伺われました。

後半は、後藤先生をコーディネータに、大木清志さん(農業経営主)、菊一敦子さん(生活クラブ生協埼玉 理事)、竹ノ谷昭彦さん(JAいるま野 営農部長)によるパネルディスカッションです。
川越市内で畑4ha、雑木林3haを経営する大木さん(農家の7代目)からは、公民館活動や女性グループと連携した体験イベント等の取組の様子をスライドを用いて分かりやすく説明頂くとともに、雑木林は評価額が高いために一部農地にした時には「ヤマ」(雑木林)を守ってきた先祖に申し訳ない思いがした、といったエピソードを紹介して下さいました。
菊一さんからは、生活クラブ生協の概要、所沢ダイオキシン騒動の際にカンパを募ったこと等の紹介の後、三富地域を体験農園、加工施設、直売所等からなる「農業テーマパーク」にしてはどうかとの提案がなされました。消費者サイドからの生活に密着した積極的な内容に感じ入りました。
竹の谷さんからは、雑木林の評価額は農地に比べて7~8割高いこと、森林施業計画の認定等を条件に4割控除の特例はあるものの、相続税の納税猶予制度が必要であること等について説明がありました。

会場との質疑応答では、ぜひ関係者が連携して対応してもらいたい、三富の野菜を特別な価値があるものとして消費者にも分かるようにブランド化すべきではないか、自分も落ち葉掃きなどできるところから参加したい等、三富地域の農業の重要性を意識した発言が相次ぎました。
一方、税制特例等については、農家がきちんと営農することが前提ではないかといった意見も出されました。
1月27日(日)には「三富千人くず(落ち葉)掃き大会」が開催され、参加者を募集中とのことです。
大震災と原発事故が契機となり、循環型の持続可能な食やエネルギーのあり方を模索していくことの重要性に対する認識が、さらに高まっています。
三富地域は地域資源循環システムのモデルの一つです。ぜひ多くの方にこの地を訪ねて頂き、様々な活動に参加することによって、その意味と内容を実感して頂くことを期待しています。
さて、私個人は「グローバル化」の行き過ぎた部分は是正すべきと考えていますが、現在のグローバル経済が自然に与えられた訳ではないことも、忘れてはなりません。
つまり、リスクをいとわず地球の各地に進出した多くの企業人の方たちのお陰で、私たちは安価な食やエネルギーの恩恵に浴していることは、まぎれもない現実です。
北アフリカのアルジェリアで発生した人質事件は、想定されうる最悪といえる結果となってしまいました。
22日22時現在、未だ邦人3名の方の安否が不明です。
不当にも生命を奪われた方達の無念さ、ご家族の皆様の悲しみを思うと、発すべき言葉も見つかりません。
【ご参考】
◆ ウェブサイト:フード・マイレージ資料室
◆ メルマガ :【F. M. Letter】フード・マイレージ資料室 通信
(↓ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして下さい。)
![]()
人気ブログランキングへ

-より豊かな未来の食のために-