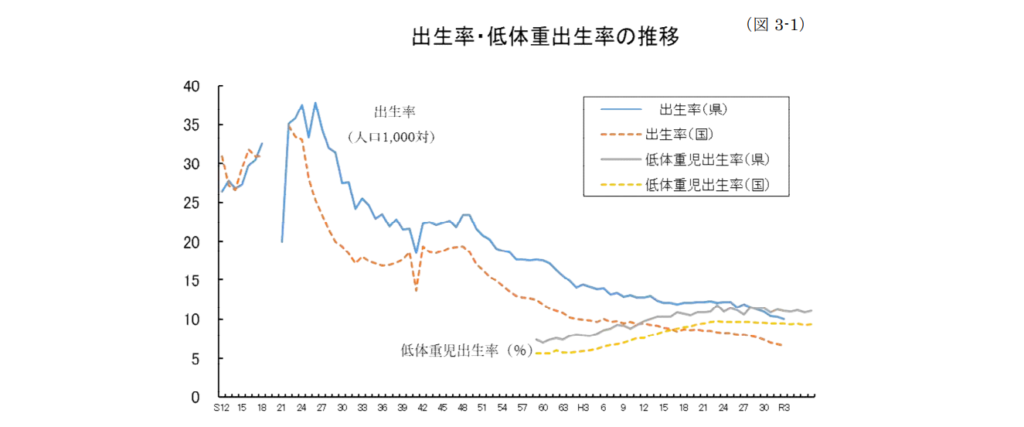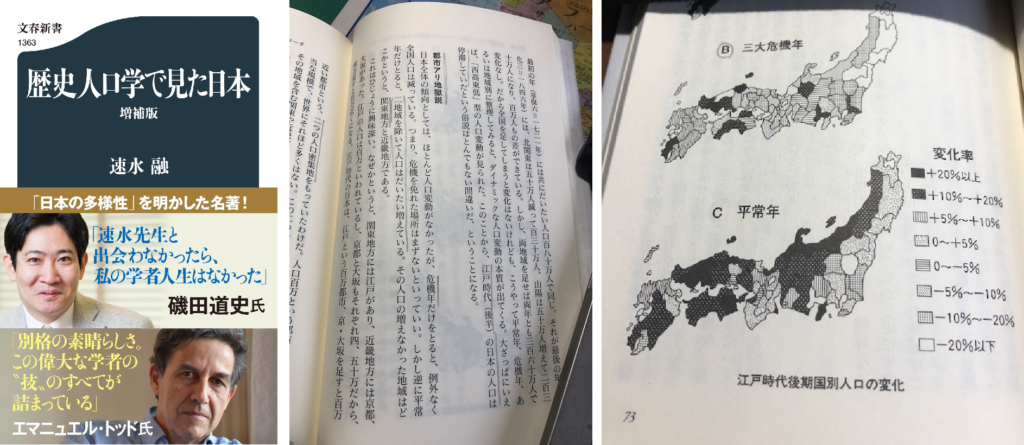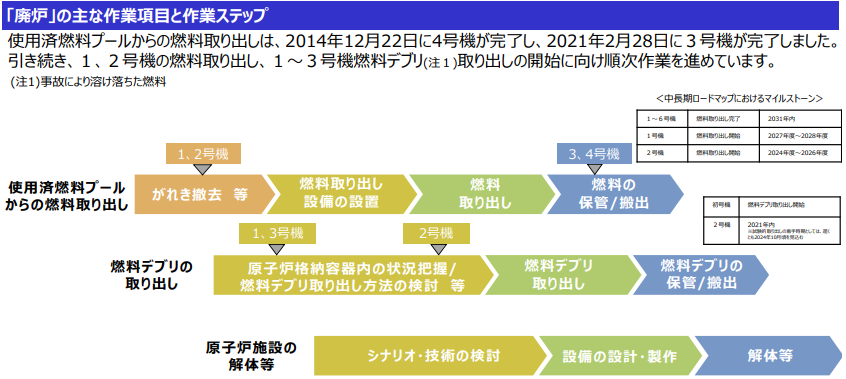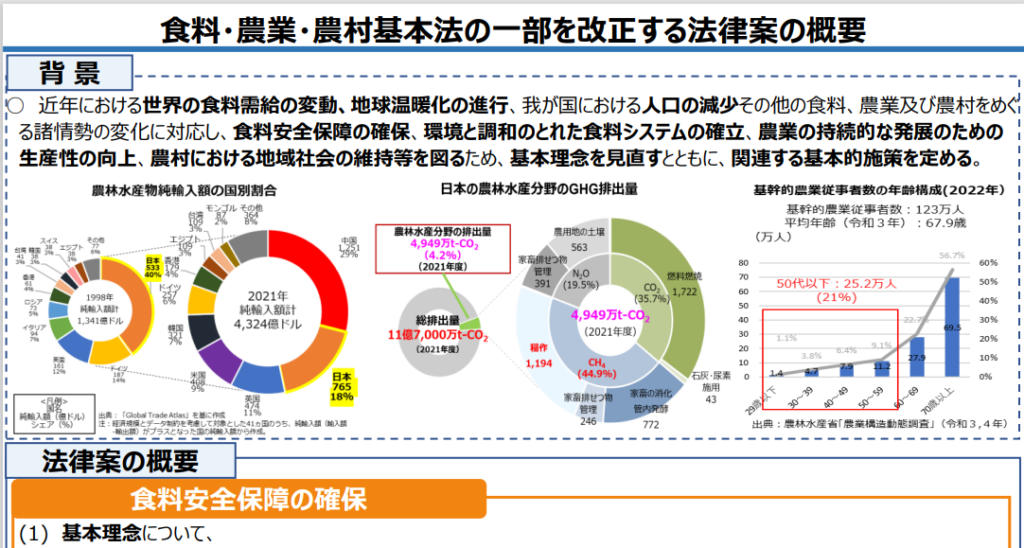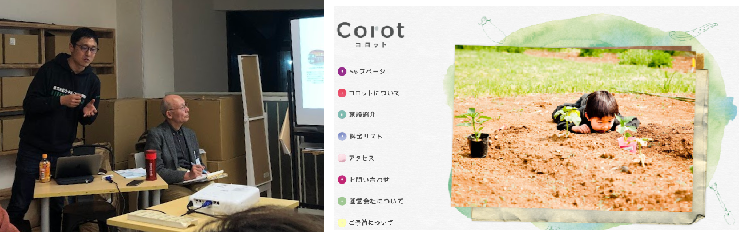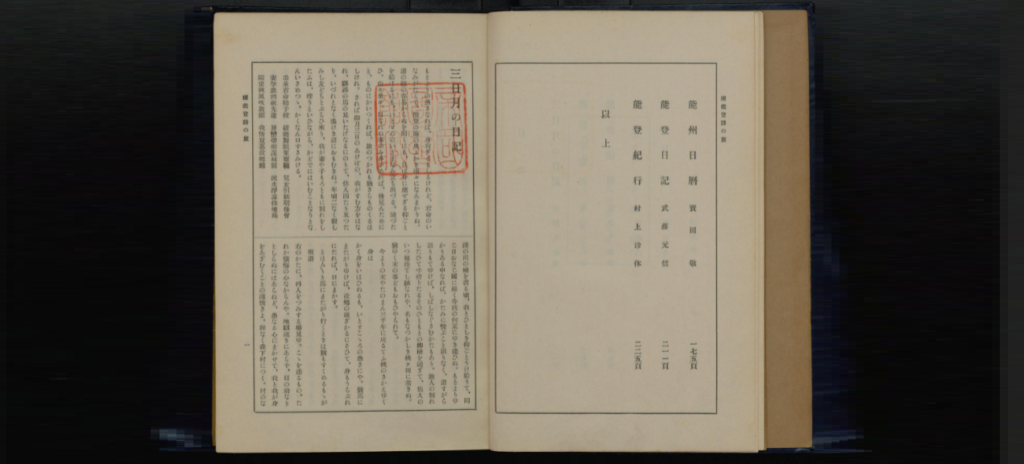【ポイント】
ご飯一杯分の米の値段は約30円。缶コーヒー、お菓子、カップ麺等と比べても非常に安いものとなっています。

先日、小農学会事務局の佐藤弘さんが興味深いポスターを送って下さいました。以前に元九州大学助教の佐藤剛史先生と一緒に作られたものだそうです。
https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2024/07/gohan_ippai-scaled.jpg
A4版の黒を基調としたポスターの中央には、湯気の出ている一杯のご飯の写真。右側には「ご飯一杯の値段」というロゴがあり、「5kg=2000円として1kg=400円、茶碗一杯約30円」との説明。上下には、缶コーヒー1/3本、チョコボール4個、カップ麺5分の1杯、コンビニおにぎり1/4かけら等の写真が並んでいます。これらはいずれもご飯一杯分の値段に相当する量です。… 続きを読む