−山下一仁『日本が飢える! 世界食料危機の真実』(2022/7、幻冬舎新書)−
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344986626/
【ポイント】
減反廃止により規模拡大とコスト削減を進め、輸出を促進し、米価下落の影響を受ける生産者には直接支払いを行うべきと主張しています。… 続きを読む

-より豊かな未来の食のために-
「F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-」のなかで、食や農の分野について考えるヒントとなる本の「さわり」だけを紹介しています。
−山下一仁『日本が飢える! 世界食料危機の真実』(2022/7、幻冬舎新書)−
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344986626/
【ポイント】
減反廃止により規模拡大とコスト削減を進め、輸出を促進し、米価下落の影響を受ける生産者には直接支払いを行うべきと主張しています。… 続きを読む
−太田昌秀『決定版写真記録 沖縄線』(2014/5、高文研)−
https://www.koubunken.co.jp/book/b202015.html
【ポイント】
沖縄戦では、動員された学徒を含む多くの子どもたちが命を落としました。その惨劇の記憶が、現在も子どもを「宝」として大切にする想いにつながっているような気がしてなりません。… 続きを読む
−河合雅雄『子どもと自然』(1990/3、岩波新書)−
https://www.iwanami.co.jp/book/b267932.html
【ポイント】
著者は、子ども時代には、36億年もかかって創り出された様々ないのち(自然)の中に自分を位置付けて考える機会が必要としています。
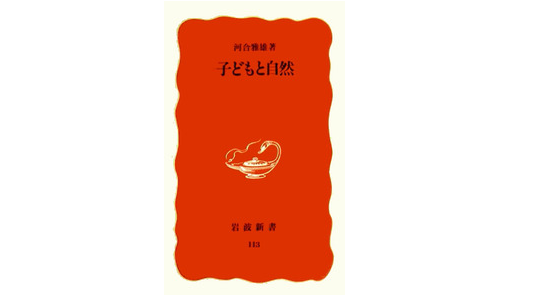
著者は1924年兵庫県生まれの霊長類学者。京都大学名誉教授、(財)日本モンキーセンター所長等を歴任し、2021年に逝去されました。… 続きを読む
−アリス・ウォータース『スローフード宣言−食べることは生きること』(2022/11、海士の風)−
https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_90993402/
【ポイント】
著者はファストフードとスローフードを対峙させつつ、「食べることは生きること」「何を食べるかが世界に大きな影響を与える」と主張しています。

1971年、著者はアメリカ・カリフォルニア州バークレーに「シェ・パニーズ」をオープンしました。オーガニックとローカルをコンセプトに「顔のみえる食材」を提供するレストランは、現在、最も予約が取りにくい店と言われているそうです。… 続きを読む
−宇根 豊『農はいのちをつなぐ』(2023年11月、岩波ジュニア新書)−
https://www.iwanami.co.jp/book/b635087.html
【ポイント】
「田んぼ」は「いのちといのちをつなぐ」場所。「田んぼの見回り」の具体的な効果についても分析的に記されています。… 続きを読む
−速水 融『歴史人口学で見た日本−増補版』(2021/5、大垣書店)−
https://books.bunshun.jp/articles/-/7202
【ポイント】
著者が江戸時代を対象に分析した「都市アリ地獄説」は、現代もスケールを拡大しつつ厳然と成り立っています。… 続きを読む
−岩井吉彌『山村に住む、ある森林学者が考えたこと』(2021/5、大垣書店)−
https://www.books-ogaki.co.jp/post/38904
【ポイント】
日本の林業・森林が急速に荒廃している元凶は林業経営の採算の厳しさにあるとし、今後は「家族林業」による副業を重視し、さらに都市住民の森に対する関心の高まりに注目しています。
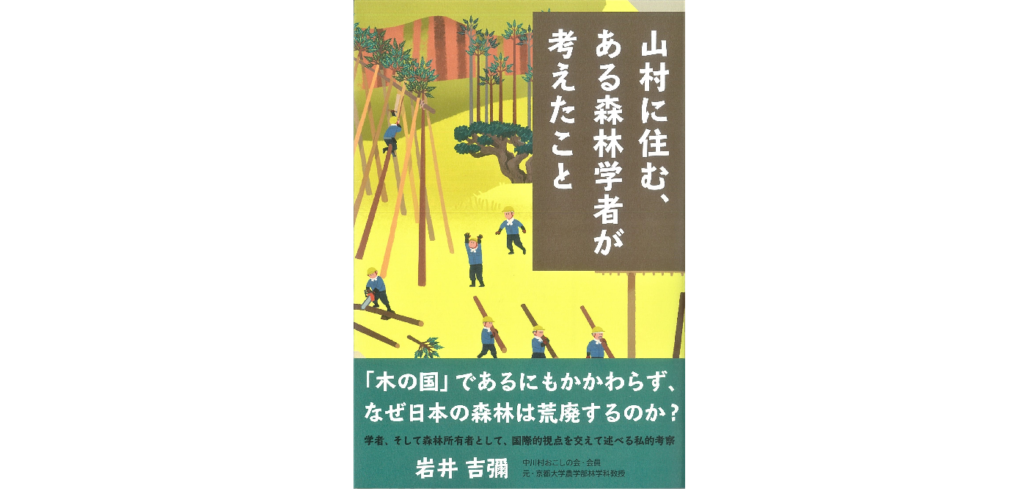
著者は1945年京都生まれ。実家は北山杉で有名な京都市北山で代々林業を営んでおり、自身も林業経営と大学教授という「二足のワラジ」を履いてこられた方。… 続きを読む
【ポイント】
都市と農村の不平等な関係を解消するためには、環境や風景に配慮した農産物が生産され、それらを消費者が積極的に選択すること(風景をつくるごはんを食べること)が必要としています。
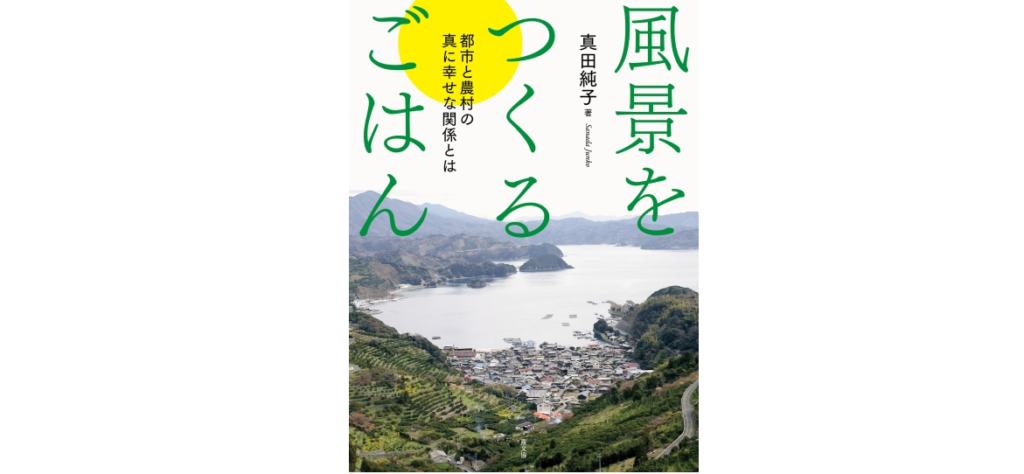
−真田純子『風景をつくるごはん−都市と農村の真に幸せな関係とは』(2023.10、農山漁村文化協会)−
https://toretate.nbkbooks.com/9784540231247/
著者は1974年広島・福山市生まれの東京工業大学教授(景観工学)。2013年には農地の石積み技術を継承するため「石積み学校」を立ち上げられました。… 続きを読む
−青木美希『なぜ日本は原発を止められないのか?』(2022.11、文春新書)−
https://bunshun.jp/articles/-/67655
【ポイント】
日本が原発を止(や)められないのは、原子力ムラが存在しているから。しかし原発は巨大だから変えられないというのは嘘で、推進する勢力は一部だけ。
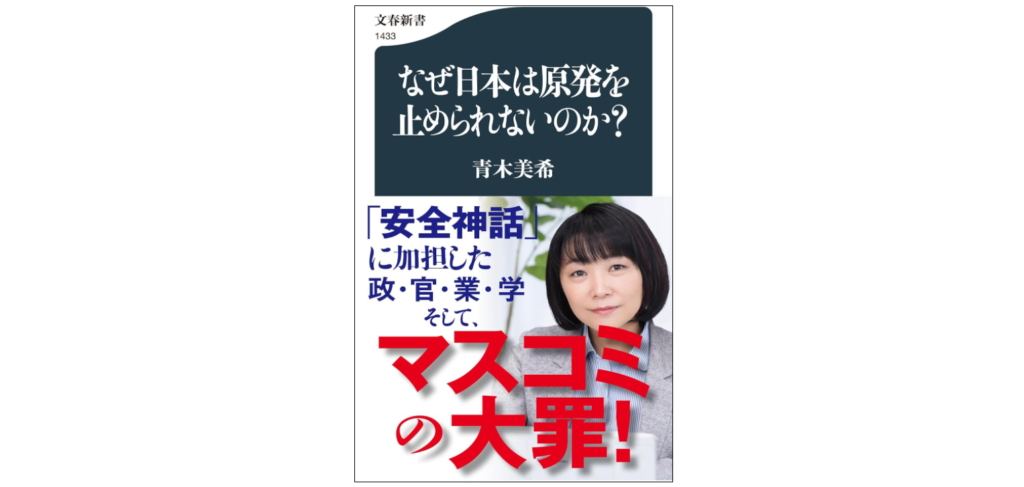
著者は札幌市出身。地元新聞社を経て全国紙に入社後は東日本大震災・原発事故の現場を取材し、「手抜き除染」の告発報道等に携わられました。現在も個人の立場で、学生時代からのライフワークである原発問題の取材を続けておられます。ちなみに祖父は電力会社勤務、父親は大学工学部の教授として原発に代わる発電方法の研究をされていたそうです。… 続きを読む
−蔦谷栄一『生産消費者が農をひらく』(2024.1、創森社)−
https://www.soshinsha-pub.com/bookdetail.php?id=436
【ポイント】
著者は、「生産消費者」がキーとなって「農的社会」を広めていくことが、日本の世界的・歴史的な役割であり責務であるとしています。
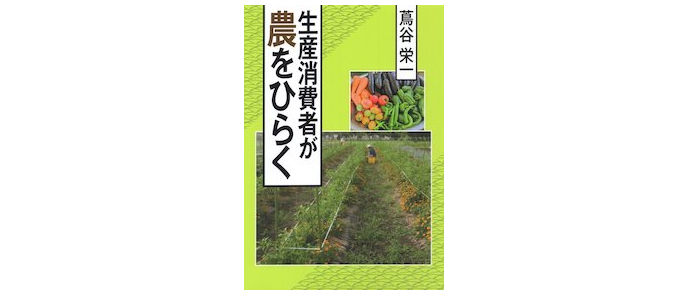
著者は宮城県出身。農林中央金庫熊本支店長、農中総研特別理事等を歴任し、現在は農的社会デザイン研究所を主宰し、様々な活動に取り組んでおられます。… 続きを読む
−平賀 緑『食べものから学ぶ現代社会−私たちを動かす資本主義のカラクリ』(2024.1、岩波ジュニア新書)−
https://www.iwanami.co.jp/book/b638607.html
【ポイント】
まずは資本主義のカラクリを知り、その逆を、自分から主体的に行くことで、人も自然も壊さない経済を草の根的に広げていけると著者は訴えています。… 続きを読む
−吉井たくみ『鷹のつらきびしく老いて 評伝・村上鬼城』(2023.9、朔出版)−
https://saku-pub.com/books/taka.html
【ポイント】
著者は「『真情の俳句』を詠んだ村上鬼城の世界観は、これからの持続可能で新しい世のなかを導く一つの力になるのではないか」としています。… 続きを読む
−吉田俊道『図解でよくわかる 菌ちゃん農法−微生物の力だけで奇跡の野菜づくり』(2014.1、家の光協会)−
https://www.ienohikari.net/book/9784259567828
【ポイント】
菌ちゃん(微生物)の力を借りた元気野菜づくりについての、初心者にも分かりやすいガイドブック。市民農園や家庭菜園での野菜作りにも、大いに重宝しそうです。… 続きを読む
−山脇史子『芝浦屠場千夜一夜』(2013、青月社)−
https://seigetsusha.co.jp/booklist/CWc5Ckok
【ポイント】
最初は1週間だけのつもりだった体験取材が7年間も続いたのは、芝浦には類いまれな、抜け出せないほどの魅力があったから。ただ、本書は出版までに四半世紀という長い年月が必要でした。
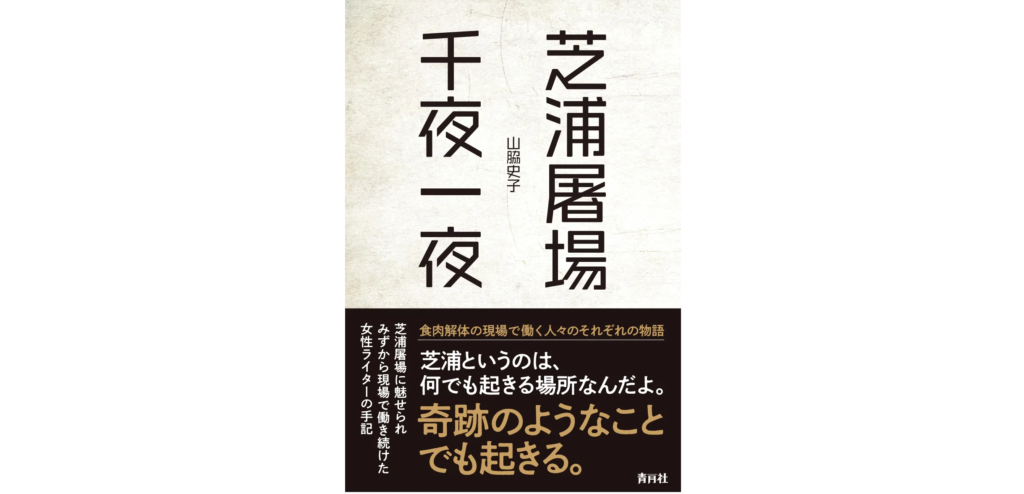
東京出身のフリーランスのライターが、1991〜98年の間、東京・芝浦の食肉市場・と場に通って現場の方から仕事を習い、働いた時の体験記です。… 続きを読む
−写真集『いつもののと』(2013.6、ゆるり能登GIAHS写真部)−
https://notostyle.shop-pro.jp/?pid=87686937
【ポイント】
人が自然と調和し、ともに生きる能登の暮らしを映しとった美しい写真集の頁をめくるに、ざわついていた心も次第に静まってきました。
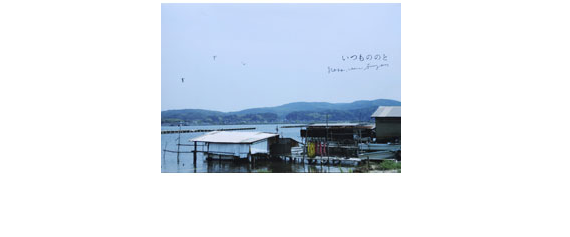
被災地からの映像に重苦しくなった心を抱えて図書館を訪ねたところ、偶然、見つけて手に取ったのが、この小ぶり(A5版)の写真集でした。… 続きを読む