先日、郷里・徳島で農家をしている友人(藍住町)がニンジンを送ってくれました。
「彩誉(あやほまれ)」という品種だそうで、見た目もきれいで、生で食べても甘さに驚きます。
職場近くの東京・日比谷公園の桜も満開です。

2016年3月30日(水)の終業後は、その日比谷公園を抜け、ご近所ラボ新橋へ。
「ご近所イノベーション」をテーマに、身近なところから、地域や社会をちょっとよくできそうな研究や実験を行っている場(港区の施設)です。
入口には「キッチン・ラボ」の立て看板。かぶとベーコンのスープが、材料費300円(お茶は無料)で誰でも楽しめるそうです。

この日、18時から開催されていた「対話の対話による対話のための読書会」(第1回)に途中から参加。
ナビゲータは、永く大学で英文学を教えておられたK子さん(「先生」と呼ぶと叱られます)。
テキストは、藤田一照/長沼敬憲『僕が飼っていた牛はどこへ行った? ~「十牛図」からたどる「居心地よい生き方」をめぐるダイアローグ~』。
A4版3頁の詳しいレジュメを準備して下さっています。
まず、「自分にとって本当に大切なものは何か」というK子さんの最初の問いかけに対しては、参加者からは家族、友人、時間、命、ありのままの自分であること、等の回答。
続いて、もしそれを失ってしまったらどうするかという問いには、なかなか想像が及ばず、明確な答えは出ませんでした。
そして、生命とは何か、科学ではカバーできない部分があるのでは、等について話し合い。
テキストを読み解くというよりは、テキストにあるキーワードをヒントに「対話」し合うという自由でざっくばらんな内容です。最後の「感想」は、次回に向けての宿題になりました。
今後は毎週水曜日の18時から、4回程度をかけてテキストを読んでいく予定とのこと。
テキストを下読みできなくてもレジュメを準備して下さるそうですので、関心を持たれた方は覗いてみて下さい。
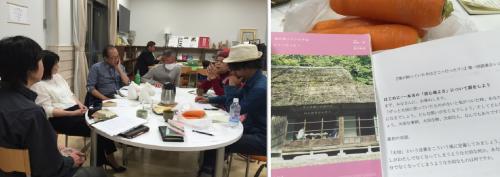
10分ほどの休憩を挟み(この間に持参したニンジンをスティックに)、19時過ぎからは、毎週定例の「対話ラボ」がスタート。
対話に関係する「研究」を持ち寄り、1年をかけて進めていこうという趣旨で、現在は研究テーマを募集している状況です。
まずは、恒例の「チェックイン」。
参加者から1人ずつ、この場に期待すること、伝えたいことについてシートに書き込み短時間で発表。
研究テーマについて詳しく話を聞きたい、対話ラボのイメージがより明らかになっていくことを期待する等から、「ミツバチの巣箱を注文した」等の近況報告まで。
そして、Fさん(男性)から提案のあったテーマ(エントリー第1号)について話し合い。
Fさんの研究タイトルは「ラボ新橋哲学カフェ」。
「哲学カフェ」は、社会や生活に関わる基本的な疑問について話し合い、自分と他人の考え方の違いを理解し「新たな問い」を探し出すことが狙いだそうです。
Fさんは各地で開催されている哲学カフェに参加されているそうで、新橋(港区)でもやりたい、ということのようです。
これに対しては、単に開催するということではなく、例えば、開催に際しての工夫や課題等を明らかにすることを目的とすることで、より「研究」にふさわしい内容としてはどうか、等のコメントが出されました。
いずれにしても、「哲学カフェ」自体は興味深い内容で、4月中には第1回を開催する方向になりました。楽しみです。
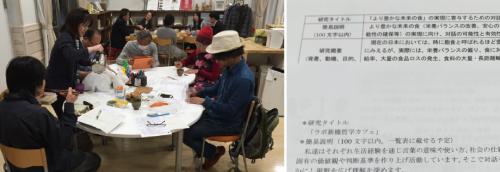
私からは、「仮」登録してある食や農に関わる研究テーマについて報告。
身近な「食」の問題について、消費者1人ひとりの自覚と実践を促していくための「対話」の可能性や有効性を探求する、ということを考えているのですが、具体的な到達点がイメージできない等のアドバイスをもらい、引き続き検討することに。
そして、最後は1人ずつからチェックアウト。
キーワードの一つである多様性を言葉に具体化できるような研究をしたい、他の人にも見えるようにトライアルとして何でも始めてみてはどうか、読書会とリンクできないか、より効率的な対話のあり方も考える必要では、等のコメント。
複数の方から、ニンジンは美味しかったという感想も頂きました。
対話ラボは、毎週水曜の19時から開催されています。
ざっくばらんな場ですので、対話に関心のある方、ご近所ラボ新橋という場に関心のある方など、良かったら顔を出してみて下さい。もし興味を持たれれば、自らテーマを立てて、プロジェクタやセミナー室も完備した恵まれた場を活用し、他の方とも連携しながら「研究」することも可能です。
【ご参考】
◆ ウェブサイト:フード・マイレージ資料室
(プロバイダ側の都合で1月12日以降更新できなくなったことから、現在、移行作業中です。)
◆ メルマガ :【F. M. Letter】フード・マイレージ資料室 通信
(↓ランキング参加中)
![]()
人気ブログランキングへ

-より豊かな未来の食のために-