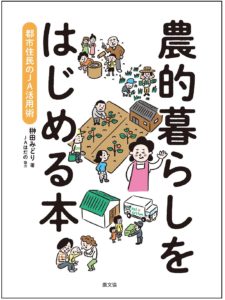
−榊田みどり『農的くらしを始める本−都市住民のJA活用術』(2022.1、農山漁村文化協会)−
https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54021235/
著者は秋田県生まれ。生協勤務を経て、現在はフリーの農業ジャーナリスト、農政ジャーナリストの会副会長、明治大学客員教授。農水省の核種検討会の委員等も勤められています。
「豆知識」「オーシャンカレント」欄でみてきたように、様々な施策が講じられているものの新規就農者数が十分に確保されていないなか、神奈川・秦野市における先進的・ユニークな取組みはかねて注目されてきたところですが、本書は、その全体像を詳しく明らかにしているルポルタージュです。
著者が注目しているのは、狭い意味での(農業を仕事とする)「新規就農者」だけではありません。
若い世代を含む都市住民等の中には、農業に触れてみたい、体験してみたい、自分で野菜を育ててみたい、プロの農家になりたいといった、多様な農に対するニーズが高まっています。しかし現実には、特に都市住民等がプロ農家として農業に参入することについては、法制度を含めて高いハードルがあるのも事実です。
ところが秦野市では、市、農業委員会、JA(秦野市農業協同組合)が連携して2006年に「はだの都市農業支援センター」を創設し、非農家の都市住民が求める農との関わり方のグラデーションに応じて、さまざまな受け皿(バックアップ体制)を用意しているのです。
例えば、ちょっとだけ農に触れたい人には「農業満喫CLUB」、自ら野菜を作ってみたい人には農業体験農園や市民農園(JAの直売施設で販売することも可能)、さらに本格的にプロ農家を目指したい人向けの「市民農業塾」など。
また、本書では、農業に留まらない「コミュニティの担い手」として受け入れている様子、制度の縦割りを超えてJAと生協が連携した取組み(共通組合員制度による「いいとこどり」等)なども描かれています。
著者にお聞きしたところによると、本書は「市民皆農」への仕組みづくりの本とのこと。
市民農業塾の講師をされている方(県外出身の新規就農者)の「畑が活かされるのであれば、なんでもありかな」という言葉が印象的でした。
出所:
F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-
No.236、2022年2月15日(火)[和暦 睦月十五日]
https://www.mag2.com/m/0001579997.html
(購読(無料)登録もこちら↑から)
(バックナンバーはこちら↓に掲載)
https://food-mileage.jp/category/br/
