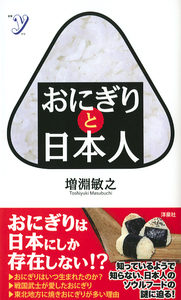
-増淵 敏之『おにぎりと日本人』 (2017.12、洋泉社y 新書) -
http://chiikizukuri.gr.jp/blog/2017/12/01/1816/
法政大学教授である著者の専門は「コンテンツツーリズム」。コンテンツ(作品)を通じて醸成された地域の物語性を、観光資源として活用することだそうです。
マンガに出てくる料理の再現レシピ集を出したことをきっかけに作品と食との関係に興味を持ち始めたという著者が、最近、最も注目しているのが「おにぎり」だそうです。
おにぎりは、米と具材、海苔のシンプルな組合せながら、様々な形、豊かな地域特性を反映した食材など、創造性に満ち溢れているとのこと。
最古のおにぎりは弥生時代の遺跡(石川・中能登町)から発掘されていること、米をまとめる(むすぶ)行為は一種の祈祷であった可能性があること、鎌倉時代以降は戦時の携行食として普及した等の歴史が語られます。
そして1970年代にコンビニが登場することによって、おにぎりは国民食としての地位を固めました。現在、コンビニでは年間60億個(!)ものおにぎりが販売されているそうです。
また、冷たいものを手づかみで食べるという食習慣は、日本特独特のものだったそうですが、おにぎりが登場する日本製アニメ等を通じて、今やおにぎりはアメリカやアジアに進出、現地化されているそうです。
さらに、おにぎりが登場するアニメ(『千と千尋の神隠し』等50本近く)について分析し、おにぎりは一緒に食べる相手との関係を象徴する食べ物であるとしています。つまり、手で握るおにぎりを食べることは、信頼関係に基づく身内と他人との線引きになっているというのです。
巻末近くには、全国各地のオススメおにぎり店や美味しいおにぎりレシピの紹介もあります。
そして最後に著者は「おにぎりを食べることは日本の食の歴史を知ることであり、その地域の特色を味わうことでもある。これほど豊かな食べものを楽しまない手はない」と「むす」んでいます。
************************************
出典:F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-
https://archives.mag2.com/0001579997/
No.162
(過去の記事はこちらにも掲載)
http://food-mileage.jp/category/br/
