新年のご挨拶を申し上げます。
例年通り、穏やかに年が明けたと思っていたら、14時半頃に地震。多摩東部は震度3と揺れは大したことは無かったものの、震源が遠かったせいか揺れの時間が長く、冷やりとしました。
昨年の大震災以降、日本列島近辺は地殻変動期に入ったという説もあり、当然ながら、年が改まったというような人間の都合など、大地には関係のあるはずもありません。
いつものように地元の大岱(おんた)稲荷神社に初詣。毎年、初詣も地産地消です。
ここでの楽しみは「地口行灯」(じぐちあんどん)。これは、駄洒落のような言葉遊びと、それに合わせた絵を書いた行灯で、東京地方の稲荷神社では祭礼等の際に飾る風習があるとのこと。… 続きを読む
「日常」の大晦日
「市民研」クリスマスパーティー
「笑顔になれる! 江戸東京野菜カレーパーティー」
新宿区立大久保小学校では、新宿の伝統野菜・内藤唐辛子や大久保ツツジを栽培したり、江戸東京・伝統野菜研究会の大竹道茂さんや料理研究家の酒井文子さん… 続きを読む
「未来を創る! 開墾牛を食す会」
12月14日(水)の夜、神田の「ちよだプラットフォームスクウェア」では、「子牛で開墾プロジェクト」の一環として「未来を創る! 開墾牛を食す会」が開催されました。
主催したのは「… 続きを読む
「呑みマス!ニッポン」
「呑みマス!ニッポン」という集まりがあります。
もともと日本酒好きの女性達が神田「なみへい」に集い、各地の銘酒を楽しむという「女子会」だったそうですが、3.11月以降、東北や北関東の蔵の日本酒を飲むことで被災地を支援しようという趣旨に衣替えされ、男子もオッサンも参加可能となりました。毎月1回、原則として11日に開催されています。… 続きを読む
フードデザート問題、新宿での復興市場
NY? マカオ? それとも東京ディズニーランド?

・・・等と規模は比べるべくもありませんが、地元の駅前広場には今年もイルミネーションが飾り付けられました。
今は日本でも普通に見られるようになっていますが、特に今年はエネルギーや節電について議論されている中、複雑な気持ちが無くはありません。しかし一方で、このような世情だからこそ、せめて街を明るく、ということも大事でしょうし、LED採用等で消費電力を減らす取組も進んでいるとのこと。… 続きを読む
向日葵、開花。
12月8日(木)の東京は、午後から雨が落ちてくる寒い一日でした。
畑に立ち寄ってみると「福島ひまわり里親プロジェクト」で植えた向日葵が、1輪はほぼ満開、もう1輪も花を開いていました。


隣にはキャベツとブロッコリ、完全に冬の装いです。… 続きを読む
永遠なれ 「野の文化学習会 in 横瀬」
2011年12月4日(日)は特別な日でした。
この日、埼玉県横瀬町宇根地区を舞台に20年間続いてきた「野の文化学習会 in 横瀬… 続きを読む
師走の向日葵、日比谷公園の銀杏
12月3日(土)は朝から荒れ模様の天候でしたが、昼過ぎには雨も上がり気温もやや上昇。
畑(市民農園)を訪ねてみると、ここ数日、寒い日が続いていたにもかかわらず、「福島ひまわり里親プロジェクト」で植えた向日葵が一輪、半分ほど花をほころばせていました。植えるのが遅く、ここのところ葉もしおれ始めてので、やはり開花は無理かとあきらめかけていましたが、嬉しい予想外れです。
気がつくと師走、その冬空に向かってまっすぐと、向日葵の黄色い花弁が伸びています。… 続きを読む
地域からの潮流。 大阪、新座。
11月25日(金)は大阪へ。
東海道新幹線の車窓からは、冬晴れの空を背景に富士山がくっきり。新大阪から市営地下鉄とニュートラムを乗り継いで大阪南港ベイエリアへ。地下鉄の車中では、日曜に迫った知事・市長ダブル選挙の投票を促す車内放送。

この日、大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)主催のセミナー「… 続きを読む
ふるさと、小平 「ダ」!
八十八卵、収穫祭、そして冬の日のひまわり
今週の農林水産省「消費者の部屋」特別展示は「熊本県のこだわり(飼料用米給与)畜産物!~『えこめ牛』・『八十八卵』の取り組み~」。11月18日(金)までの10~17時(ただし最終日は13時まで)の間、開催中です。
八十八卵(やそはちたまご)とは、熊本県宇城市の那須ファームさん… 続きを読む
TEIKEI, 距離を縮めるために
11月6日(日)は小雨模様のなか「恵泉祭」が開かれている恵泉女子学園大学(多摩市)へ。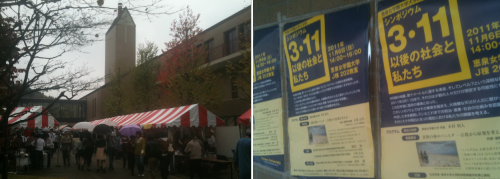
シンポジウム「3・11以後の社会と私たち」は、大教室に立ち見が出るほどの満席。
木村利人学長の挨拶に続き、福島県三春町の福聚寺住職で芥川賞作家でもある玄侑宗久氏による基調講演「異教の神のパニヒダ -宗教から原発を考える-」。パニヒダとはギリシャ正教会等で行なわれる通夜のような儀式のこと、「異教の神」とは原発のこと。これを日本古来のアニミズム的な土壌に受け容れたことの失敗について話されました。結論は「異境の神」原発の通夜をしましょう、と。… 続きを読む
身近にある歴史との対話
11月3日は文化の日。
「しごと塾さいはら」の蕎麦刈りの日だったのですが、追い込みの仕事の疲労感が抜け切らず、遠出はパスすることに。
その代わり、地元H市内を自転車で散策。
曇り空で陽射しは乏しいものの寒くはありません。ここのところ季節外れに暖かい日が続いています。… 続きを読む



